


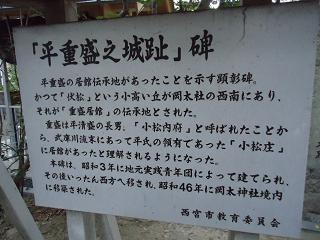



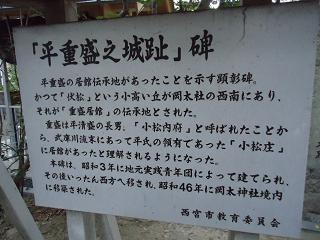
野球場・多目的広場も併設しています。

いつもスタッフの方がいらっしゃって安全に配慮していますし、売店やトイレもありますので、ビギナーの人におすすめですね。
夏に無防備で行くととんでもなく焼けます。



窓際の席は見晴らしがいいです。南の方は工業地帯ですけど。

日替わりランチ 800円。
他にもメタボレスメニューや、ビーフシチュー、ビーフピラフ、いろんなものが少しずついただける武庫川弁当などなど、和洋中と幅広くそろっています。
宝塚ホテルのケーキセットもありますよ-


「川の上にある駅」なら阪神香櫨園や芦屋・阪急夙川駅などがありますが
駅舎全体が川の上にあるという駅は、全国的にも珍しく、
東鳴尾駅。次の洲崎駅とともに無人駅です。

西宮から武庫大橋までは国鉄貨物船が、武庫大橋から阪神電鉄が走っていました。その名残が武庫川駅の北側に残っています。


阪神高速尼崎西入り口のすぐそばに、複合アミューズメント「アマドゥ」があります。レストラン・ゲームセンター・ホームセンターが入っています。日曜日にはフリーマーケット・ストリートパフォーマンスなどのイベントが楽しめます。ホームページはこちら。

尼崎市の臨海地帯にある元浜緑地は平成3年、日本で最初に作られた「大気汚染対策緑地」です。
地域の大気浄化や住民の健康保持増進を目的としています。
「もみじ池」のハスが人気スポットです。



ロングスライダーもあって、水あそびもできるんですよ。
プールではありませんので顔をつけたり泳いだりすることはできません。
更衣室はありませんが、簡易シャワーはついています。オムツをつけている子供さんの使用は禁止ですが、水遊び用のオムツは使用できます。

わんぱく池 6月-9月初旬まで
9:00-17:00 まで 開園
休園日:月曜日(祝日の場合は翌日)
雨天等の悪天候時 入園料:無料
所在地:尼崎市元浜町1丁目・尼崎市道意6丁目
アクセス:阪神 尼崎センタープール前駅から徒歩15分
開園時間:夏期(4月から9月)6:00-20:00
冬期(10月から3月)7:00-18:00
蓬莱湯
「お肌がすべすべになる」 また、ペット用温泉や温泉水自動販売機といった「アイデアの温泉」でも有名な銭湯が2009年秋にリニューアルオープンしました。専用駐輪場も完備です。


住所:尼崎市道意町2-21-2
営業時間:15:00-23:30(日曜は12:00-23:30)
定休日:金曜日










村野藤吾(1891-1984):装飾は不必要なものとして排除される傾向にあった「モダニズム」の方法によりながらも、装飾を多様。「階段の魔術師」の異名をとるほど階段や階段の手すりにこだわった建築物をたくさん残している。旧大庄村役場でも階段が緩やかに弧を描き、その曲がり方も階によって微妙に異なっている。大阪新歌舞伎座・宝塚カトリック教会・神戸の川崎製鉄所西山記念会館などの建物を残す。大庄公民館は、ノーベル賞の晩餐会が開かれるストックホルム市庁舎に感銘を受け、建築家として独立したあと最初に手がけた公共建築である。
お隣の大庄小学校 役場が建築された年の翌年には総数3000人を超えるマンモス校となりました。
「日本一裕福な村のシンボル」と「日本一のマンモス校」が隣接するということは実に珍しいことでした。

「琴浦神社」この神社は、源融光が祭神として祭られています。彼は嵯峨天皇の皇子でその邸宅京都六条の河原院に、陸奥の塩釜の風景を模して庭園をつくり、毎日30石の潮水をここから運んで、塩を焼かせたと伝えられています。また海岸の景色がよそより優れているという意味で異浦とも呼ばれていると言われています。また、潮くみについては、同じ尼崎市内にある潮江の素戔鳴神社も同様の由来を持つといわれています。

次に地名にもなっている菜切山。菜切塚は浜田町の武内家(浄専寺)に伝わる古記によれば「孝元天皇曾孫武内宿禰大臣、免位の後、難波宮松原の傍に住し給う、宿彌後此所に葬る、宿禰塚此なり」「宿禰の一子この地にとどまり朝廷に仕えた」と記されています。菜切塚は戦前までは環溝のある前方後円墳の型をしていました。昭和10年代区画整理のため環溝は東北の幹線道路となり従来の約半分足らずの広さになりました。市民に親しんでもらうため菜切山緑地として市の管理に移行されました。

熊野神社








旧尼崎警察署
1876年、西宮警察署尼崎分署として発足しました。
1916年に尼崎警察署となりました。建物は、そのとき建築されたもので、鉄筋コンクリート造3階建で、建築様式は「セセッション式」(19-20世紀初頭にかけてドイツ、オーストリアに興った芸術の革新運動から生まれた様式で、建築では、四角を基調とした様式が特徴)と呼ばれるものです。
震災までは、児童館、市役所の出張所、青少年の武道場として使われていましたが、現在は使われておらず、普段は入り口は封鎖されていて中には入れません。
耐震化工事を終え、地域に残る旧警察署を文化財として保存する運動が展開されていて、1年に1回公開されています。
入り口には急な階段があり、「バリアフリー」とはほど遠い建物です。
玄関を高いところに置くことにより「おかみ」の威厳を見せたかったのでしょうか。

明治・大正時代に使われていた地下の留置所には
灯りも窓もない狭く暗いところで、複数人が閉じ込められていたそうです。
壁に落書きが生々しく残ります。

尼崎市立文化財収蔵庫
市立尼崎高校の前身である尼崎市立高等女学校の校舎として建てられた建物を活用しています。尼崎市内の遺跡から発見された考古資料、寄贈を受けた民俗資料を展示し、文化財保護の事業をになっています。


開館時間 9:00-17:30
休館日 土・日・祝日・年末年始
尼崎市公設市場卸売市場では 毎月第一土曜日 8:00?11:00まで
どなたでも昔ながらの仕入体験ができる「市場開放フェア」を開催しています。

駐輪スペースもたっぷりあります。
塚口駅からレンタサイクル利用が便利です。
バスの場合は「阪神尼崎」行きの阪急バスにのり、「尾浜」で下車します。

マスコットキャラクターは尼崎市の小学生考案なんですよ。
小学校向け市場見学も受け付けています。詳しくはこちら。
お魚をさばいたり、野菜をパック詰めしているところも間近で見られますので、
子どもさんと一緒に開放フェアに行くという経験もいいかもしれません。

受付で粗品引換券を受け取り、購入店舗でスタンプを押してもらいます。
再び受付に持っていくと、粗品がいただけます。(先着500名様)


年に1度、10月頃に開催される市場フェスティバルでは、模擬せり体験、生マグロの解体ショー、メロンの試食会、子どもさんに人気のヒーローショーなどイベントもりだくさん。
飲食コーナーやフリーマーケットコーナーも設けられ、たくさんの方が訪れます。








尼崎市が応募し交付決定された国の「ふるさと雇用再生特別交付金」(平成21年度-23 年度の3年間)を活用して、尼崎にも観光所ができました。
地図・パンフレット・チラシなどを設置、自由に持って帰れます。
忍たまのイラスト入り寺町のガイドブックもありますよ〜
営業時間内は専属スタッフの方に質問や相談もできます。
遠方の方も、それほど遠くでない方も、市内の方も、外国の方も関係なく
友達の家に遊びにいくような感覚で、生活空間にあるスポットを巡ることができるのはもともと観光地として認識されていなかった強みです。
歴史スポットあり、東洋のシェークスピアを輩出し、現在では人間国宝もお住まいの文化的な町でもあり、聖地巡礼で人気を集めているだけでなく、臨海地区は工場萌えにはたまりません。
サイクリングにも最適(尼っ子リンリンロード 武庫川 猪名川)、世界一のコレクション(貯金箱博物館)からパラダイス(こども科学博物館)までいろんなミュージアムもあり、銭湯価格の温泉も充実、そして、「安ウマ」では間違いなくコールド勝ちなグルメと「歴女・オタク・グルメ・サイクリスト 誰でも歓迎 何でも作りますよー(笑)」です。




の中央商店街は、阪神出屋敷までつながっています。途中で三和商店街とクロスします。阪神タイガースや尼崎出身F1レーサー小林可夢偉氏を商店街をあげて応援しています。

尼子騒兵衛先生の絵が描かれたアーケード
安政年間(1854-1860)創業の天ぷらやさん(関西では揚げかまぼこのことも天ぷらと呼びます)尼崎枡千。もう一品のおかずに、おつまみにいいですが、1枚でも結構おなかいっぱいになりますよ-尼崎市内はもちろん西宮、芦屋、そして全国にファンをもち、午後には売り切れていることが多い、誉れのお店です。MAP
mars(マルス)1階の手前はオリジナル商品を展示販売できる「ギャラリーボックス」コーナーです。奥は主に陶器や着物リフォームバッグや洋服を揃えています。
出品には審査をしているだけあって、センスのよい商品が並んでいます。
2階は「手作り教室」で、フラワーアレンジメント・トールペイント・押し花・ビーズが学べます。尼崎市神田中通4-164
営業時間 11:00-20:00 不定休 MAP

たこふく マルスの2件隣のたこ焼き屋さん。ちちんぷいぷいや物産店でも人気です。
まるみや あっさりした甘味で一気飲みできるあめすいが名物 尼崎市神田中通5-195 10:00-18:30 木曜定休
菅原屋 車掌さんが使っていた、黒革の大きなガマ口のついた鞄を復刻させ、全国の鉄ちゃん・鉄子さんから注目されるアツイお店。
尼崎の高架下「じっと噛みしめてごらん ママの温かい心が お口の中にしみ通るよ・・・」のCMでおなじみ 「パルナス」が。なつかしいピロシキが買えます。
桜里 尼センの中にオープンした甘露園プロデュースの日本茶もある充実カフェです。
大はま 2号線沿いで1973年-2003年まで、割烹おゝ浜として、2003年からはJapanese Dining大はまとしてリニューアルオープンし、尼崎で34年親しまれてきているお店です。名物ポン酢は柑橘がきいたさわやかな味。お取り寄せもできます。
地域密着コミュニティースペース「エムアイエーステーション」

工場や直営店でしか買えなかったメイドインアマガサキの商品がそろっています。思わずなごむ癒し系湯たんぽ、航空機や空調設備のための金属加工技術を使って作ったぜいたくなボールペン、尼崎の地ソース、世界初の胡麻ドレッシング、砂糖を使わない不思議な水あめ、尼の生揚げ醤油、尼崎の風景を焼いたおせんべい、尼崎の地名がついたお茶、ピロシキ・・・などなど。

弥次郎兵衛 お米屋さん直営のお弁当屋さん。天むすは人気商品 尼崎市神田南通 3-83 8:00-17:00 木曜定休
カフェ・ド・シフォン 自宅を改装したカフェ。種類豊富な手作りケーキセットは500円。尼崎市神田中通8-264 9:00-17:00 不定休
法園寺
境内には五輪塔があり、秀吉から九州での失策の責任を取らされ切腹を命じられた北陸の武将 佐々木成政の墓と伝えられています。
成政は富山県で治水に尽力したり、真冬の北アルプス越えという離れ業を成し遂げたりしたそうです。
寺宝として後陽成天皇の直筆の和歌、「なき人のかたみの雪やしぐるらん 夕の雨に途はみえねと」と一首の掛け軸などがあります。

常楽寺
大物より寺町に移されました。
ご本尊は阿弥陀如来ですが、津田宗博という豪族が寄進したと伝えられています。お墓が常楽寺に残っています。

善通寺
善通寺は阪神間で唯一の時宗教のお寺。
赤レンガの塀が特徴です。寺町の中でも少し奥まったところにあるので異次元のようですね。
寺内には後醍醐天皇の皇子、尊良親王が土佐に流されたとき、お供をした秦武文の碑が建てられています。
妃を土佐に迎えるとき尼崎で海賊のために奪われ、ついに自決した南朝方の忠臣悲話が伝えられています。本堂は尼崎指定文化財です。

八角堂には首だけのお地蔵さんがまつられていて、「首なし地蔵」として信仰を集めています。
なぜ首だけなのに首なし地蔵というのかといいますと、境内の張り紙によると
300年以上前善通寺境内に地蔵尊がお祭りされていましたが、不届きものが首から上をちぎって庄下川に捨ててしまいました。
それから以後首無地蔵尊と呼ばれ参拝者が絶えることがありませんでした。
ある日、漁師さんの網にお地蔵さんの首がかかりました。
家に持ち帰り朝夕おまいりをしていたところ、夢枕にあらわれた地蔵菩薩が
「私は善通寺の地蔵です。元に戻してもらえれば、首から上の病をなおしましょう」とお告げがあったので
善通寺の住職にこのことを申し出て首を元に戻すと、胴と一致しました。
地蔵堂を建立して御尊体を奉仕されました。戦災によって地蔵堂は消失しましたが、首から上は無事で残り、
現在の八角堂の中にお首を祀ったということです。

大覚寺
2月3日の節分祭の豆まき、「大覚寺狂言」で有名です。

聖徳太子が百済の高僧・日羅に命じて長洲浦に造らせた「燈炉堂」が起源であると伝えられています。鎌倉末期から港湾都市尼崎の発展に大きな貢献をし、尼崎城が構築されるまでは大覚寺城として活躍しました。
中世尼崎を知るうえで欠くことのできない「大覚寺文書」は、兵庫県の指定文化財です。当時の境内や伽藍配置の記載や長洲荘領主鴨御祖社社家や荘園代官、沙汰人らが同寺の安泰を保証した証文があります。
長遠寺
本堂と多宝塔は国の重要文化財に指定されています。
本堂は入母屋造、本瓦葺です。柱の上の組物や軒屋根の傾斜などに桃山時代の建造美をうかがうことができます。
1982年の解体修理によって、1623年にこの地に再建されたことが判明しました。

多宝塔も棟札に慶長12年(1607年)とあり移築されたものと考えられています。
塔身は円形で軒そりの形がよく組物や蟇股などの形態には桃山時代の特徴がよく表れています。

客殿・庫裏・鐘楼は県の指定文化財です。
その他室町時代の銘をもつ鰐口、雲板、裏書に永禄8年(1565年)と記された絹本著色涅槃図、長遠寺文書、
紙本着色日蓮大聖人註画讃が尼崎市の指定文化財に指定されています。



如来院
古くは「神崎釈迦堂」といい創建は神崎の地です。
1327年の石造物で笠塔婆という供養等があります。笠の部分は失われています。
銅鐘とともに、尼崎市の文化財に指定されています。

また鎌倉時代法然上人が神崎に立ち寄ったとき、
極楽浄土に往生することを願って神崎川に入水した5人の遊女の髪がまつられています。
江戸時代に現在の寺町に移転しました。

専念寺
寺町の一番西にある赤い門が特徴の通称「あまもんさん」と呼ばれるお寺です。
平安末期の武将、平重盛の菩提所ということで朝廷から山門を赤くすることを許可されました。
重盛は仏法に帰依深く、冷静沈着な理想的な人間として平家物語に描かれています。

阪神尼崎駅から南へ徒歩5分のところに11箇所の寺(本興寺・全昌寺・広徳寺・甘露寺・法園寺・大覚寺 長遠寺・如来院・専念寺・善通寺・常楽寺)が集まる「寺町」
尼崎城を築城した大名戸田氏鉄が城下町を作るにあたって、散在していた寺院を集めたため、それぞれのお寺がまとまっていていて、全て徒歩でまわっていただけるという全国的にも珍しいエリアです。
城下町の防衛のために大建築の寺院をおいたとも考えられています。
全昌寺
戸田家の菩提寺として現在の滋賀県大津市に建立されましたが、
1617年戸田氏鉄が尼崎藩主として入城の際に随伴した雲山呑秀和尚によって
この地に再建されました。
戸田氏鉄は甲賀忍者とも親しかったのだそうです。

本興寺
室町時代1420年(応永27年)創建、法華宗(本門派)の古刹です。
開山堂は、国指定文化財。1466年の建立です。唐様二重扇垂木入母家撞木造りの建物は、鎌倉以西にはない豪華なもので、天井に書かれた籠絵や内陣の極彩色の模様が鮮やかである。また、安置されている、創立者の日隆聖人木像は、聖人が70歳のとき、堺の佛師浄伝に刻ませ、自ら開眼されたもので桧寄木造りで同じく国指定文化財です。開山堂は1963年解体修理されました。
開山堂の御霊水は良質で、尼崎住民の唯一の飲料水として「金水」と呼ばれ、1916年に水道が敷設されるまで市民の貴重な飲料水として親しまれました。
一度沸かしてお飲みくださいとのことです。
鐘楼は兵庫県指定文化財。阪神・淡路大震災の修復の際、天文年間の建物であることが判明しました。朝夕に梵音を響かせ、除夜の鐘でも有名です。
国指定文化財、方丈は1548年の建立です。1617年に現在地に移転し、大規模な修復が行われました。書院造りの様式は古来、「客殿」と称され、絵画、襖絵群は1980年解体処理、創建当時の姿に復元されました。
方丈の内部は普段見ることはできません。
方丈の小堀遠州の作と伝えられる枯山水の築庭です。本堂屋根瓦の流れを滝に見立て、幽玄の景を偲ばせます。
伏見宮家や尼崎歴代城主の接待所としても使われた、壁画や襖絵、畳の間も広くて立派なものでした。
国指定文化財、三光堂には、三光天使、鬼子母神、十羅刹女、三十番神が祀られています。虹梁、木鼻、手狭、蟇股、欄間の彫刻は桃山建築の特色を現しています。
宝物殿。一階ホールには白髪一雄画伯の「皆応供養」の作品、上田秦江画伯の「一天四海運」の作品が飾られています。数珠丸(日蓮大聖人御所持の刀)兵庫県指定文化財の禁制や銅鐸を始め、ご本尊、法宝物、絵画、漆器、茶碗、屏風などを所蔵しています。毎年11月3日の「虫干会」の際に公開され、たくさんの方が訪れます。
広徳寺
1582年、本能寺で織田信長が明智光秀に倒されたとき、遠征先から急いで戻ってきた秀吉は途中軍勢をはなれ、智方の武将に追われて逃げ込んだというお寺です。そこで髪をそって僧に化けて台所で味噌をすっていた僧の中にまぎれこみ、追っ手から逃れたといいます。

そのときにつかったというすり鉢とすりこぎが広徳寺に伝わっています。

甘露寺
1771年寂誉上人代に信者岸田屋浄順の請願によって城主松平遠江守は常行念仏三昧道場の許可を与えました。それ以来、今日に至るまで別寺念仏会を修行しています。

1991年、桃山時代の様式を取り入れて改築された本堂、西方浄土極楽鳳停止殿の屋根の凰です。
阪神電車に乗っていても見える迫力満点の鳥居。
尼崎えびす神社は、尼崎の古名「琴の浦」ゆかりの神社です。
菅原道真公が「ここは殊のほかよき浦なり。松は琴柱の並びたるが如し」と褒め称えました。
福の神として年間50万人の尊栄を集める神社となっています。
10日えびすの日は、それはそれはたくさんの人と、屋台、そして、神社の周囲のお店の臨時出店も立ち並びます。

尼信記念館
尼信博物館前にあり、尼崎信用金庫の旧本店を明治時代に建築された当初の赤レンガをそのまま使って復元したものです。
尼信博物館には、「城下町尼崎展」コーナー、世界170国のコイン2500枚を見ることの出来るコインミュージアムがあります。すぐ近くには、世界一のコレクションを誇る世界の貯金箱博物館も。

43号線を越えたところにある中在家町は、1618年に開始された尼崎城の築城にともなって、住人らを城の西方に移らせ新たに建設し、魚市場・魚問屋で栄えた町です。近世には瀬戸内海一帯の魚が集散し、京都や大阪に出荷していましたが、漁船が直接大阪に入港したり、鉄道敷設にともない衰退していきました。震災後は当時の面影をほとんど失っています。魚の集散地である尼崎らしい産業として、かまぼこ・てんぷら・醤油などの水産品加工業が盛んになりました。

参考文献 尼崎絵地図(国土交通省 近畿地方整備局 神戸港湾事務所発行)・図説尼崎の歴史

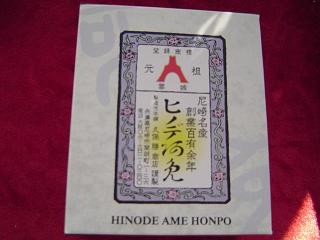





東部第一浄化センター
屋上にはアスビ(アマガサキ・スカイ・ビオトープ)と公園を設置。高度下水処理水を利用したビオトープです。さまざまな生き物と共生できる環境の保全・復元をはかります。尼崎臨港の風景が360度パノラマで見渡せます。

初嶋大神宮
静かな海原に浮かぶ小船、点在する砂洲の島々。「歌枕 浦の初島」と呼ばれた景勝地でした。「大和物語」や谷崎潤一郎の「蘆刈」のモチーフになりました。「鎌倉時代末期以来、別所町(現在の東本町)にあったといわれる初島恵比寿が江戸時代の城下町開発とともに築地町に移され、初島大神宮になりました。9月に「築地だんじり祭り」が行われています。


江戸時代に尼崎城の城下町の一つとして誕生し、近世以来の碁盤の目状のまちなみが残っていた築地で長年愛されてきた銭湯です。
2002年に源泉かけ流しの温泉が登場しました。
こちらは380円(サウナ使用料は240円)で入ることができます。
露天風呂もありますし、エステバス、リラックスバス、ローリングバス、塩サウナなども併設しています。

住所 尼崎市築地2-2-20
営業時間 10:00-24:00(土・日・祝は7:00-)
定休日 第2・4木曜(祝日の場合は営業) 1月1日
アクセス:阪神尼崎または大物から徒歩10分
参考文献 尼崎絵地図(国土交通省 近畿地方整備局 神戸港湾事務所発行)・図説尼崎の歴史
尼崎病院を囲む公園です。東側の墓地には1864の蛤御門の変のとき、京都から帰国の途中大物で捕らえられ、自決した「残念さん」と呼ばれている長州藩士・山本文之助の墓があります。MAP
SLD518(デゴイチ)が展示されています。重量は機関車が68.5トン、炭水車38.2トン 長さ19.5メートル 高さ3.98メートル 幅2.8メートル。走行距離は地球と月3往復分にあたります。4月から11月の第三日曜日の10:00-12:00 13:00-16:00に開放されます(天候が悪いときは中止)お問い合わせは教育委員会青少年育成課(尼崎市立青少年センター 06-6429-3020)まで
尼崎城刻印石
1950年頃城内小学校南側南門(旧尼崎城内大手門付近)にあった工場跡地から発掘されたもの。本丸の堀の石垣に使われていたものと推定されます。
大日本紡績 尼崎工場跡(現在の大物公園・小田南公園・県立尼崎病院一帯)に作られた広い公園。野球場・運動広場。日本庭園のような散策スペース・噴水・梅の木もあります。自動販売機もあるのでお弁当やパンを持っていって食べるのもいいですね。
大物くずれの戦碑
応仁の乱をきっかけに戦国時代となった頃、室町幕府の実権を握った細川氏も、内部で対立してきます。細川政元の養子高国と同じく養子の澄元・晴元父子が対立し尼崎の地でたびたび戦火を交えています。1531年の両者が決戦するに至ったとき、高国勢は総くずれになり、尼崎へ逃げ込む程の大敗となりました。追撃は激しく高国は大物の「広徳寺」で自刃しました。この戦いを「大物くづれの戦い」とよんで語り伝えられてきました。MAP
阪神杭瀬駅前には網の目状に広がる商店街があります。地元の杭瀬熊野神社では福を授けながら、おみこしが町を練り歩くのだそうです。
浄光寺
真言宗の別格本山であり、弘法大使がこの地に立ち寄り創建したといわれています。「紙本着色浄光寺縁起図」には、天長年中に釈恵満という僧が海中より放光する金像を得て歓喜するところからはじまり、次いで南北朝の内乱時には南朝方の楠木・和田勢を浄光寺を城として利用した北朝方の箕浦との合戦、寺の焼亡、寺の再建と本尊の安置供養するところまでが絵巻風に描かれています。MAP

東洋紡績神埼工場跡
1900年に設立された大阪合同紡績株式会社は、1913年この地に神崎工場を建設し、翌年から操業を開始しました。1931年、東洋紡績株式会社に合併され、神崎工場も同社の工場になりました。当時は敷地面積30万平方メートル、労働者三千数百人に及ぶ大工場でした。労働者の大多数は地方出身の女工で熊本や鹿児島からも出稼ぎに来ていました。1945年、尼崎は大空襲を受け、工場は全焼、1950年閉鎖されました。工場跡地は杭瀬団地となり、現在に至っています。MAP
杭瀬の商店街
国道2号線と平行に西から、栄町商店街、杭瀬1番街、昭和ショッピングロード、園田橋線沿い(南北)には、杭瀬団地商店街、杭瀬本町商店街、昭和ショッピングロード内に南北に杭瀬市場・北市場・中市場・東市場があります。
昔ながらの喫茶店も健在


昭和ショッピングロード内にある、昭和3年創業の和菓子屋さんです。チョコレートをおもちでくるんだ「ショコラ デ ユウキ」はヒット商品です。(季節限定)
営業時間 9:00?19:00
不定休 (盆明け、正月明けの数日)MAP
おすすめ商品はテレビでも紹介されたことのあるどら焼きです。素材にこだわり、地域密着のドラ焼きを尼崎ブランドを目指して日夜がんばって焼いておられるそうです。つかしんとCOCOEあまがさきにも支店があります。
からだにやさしくて国産有機無農薬豆腐のお店です。手作りでつくりたてなのでとてもおいしいですよ。三和商店街内にも支店があります。
営業時間 7:00-19:00 定休日 木曜日 MAP
おすすめ商品はゆばとうふ。とりよせもできるパック入りと日持ちはしないけど大きめお徳サイズのものがあります。ちゅるちゅると生湯葉がはいっているなんとも珍しい食感です。蟹やホタテがごろごろ入った卵豆腐はなめらかな味で前菜にぴったりです。とろけるようなやわらかさのお豆腐白雪もおすすめ。
杭瀬の駅にあるショッピングモール「駅の街」内の甘露園では、「近松の戯」(煎茶)「金楽」(煎茶)「武庫」(くき茶)「大物」(ほうじ茶)と尼崎の地名と歴史を紹介した「銘茶尼崎散歩シリーズ」があります。営業時間 10:00?20:00 定休日 水曜日





野里商店街入り口に位置する神社です。
「野里の一夜官女」という人身御供にされた女性の言い伝えがあります。
淀川戎神社は十日戎にはにぎわいます。


駅前にある1978年にオープンしたケーキ屋さん ラ・ファリーヌ
姫島神社の祭神は阿迦留姫命と住吉大神。神崎川と中津川との間のデルタのひとつで、難波八十島の比売島(ひめじま)の産土神をまつったと考えられます。万葉集にこの地に関して次のような和歌があります。「妹が名は 千代に流れん姫島の 小松か末に こけむすまてに」
